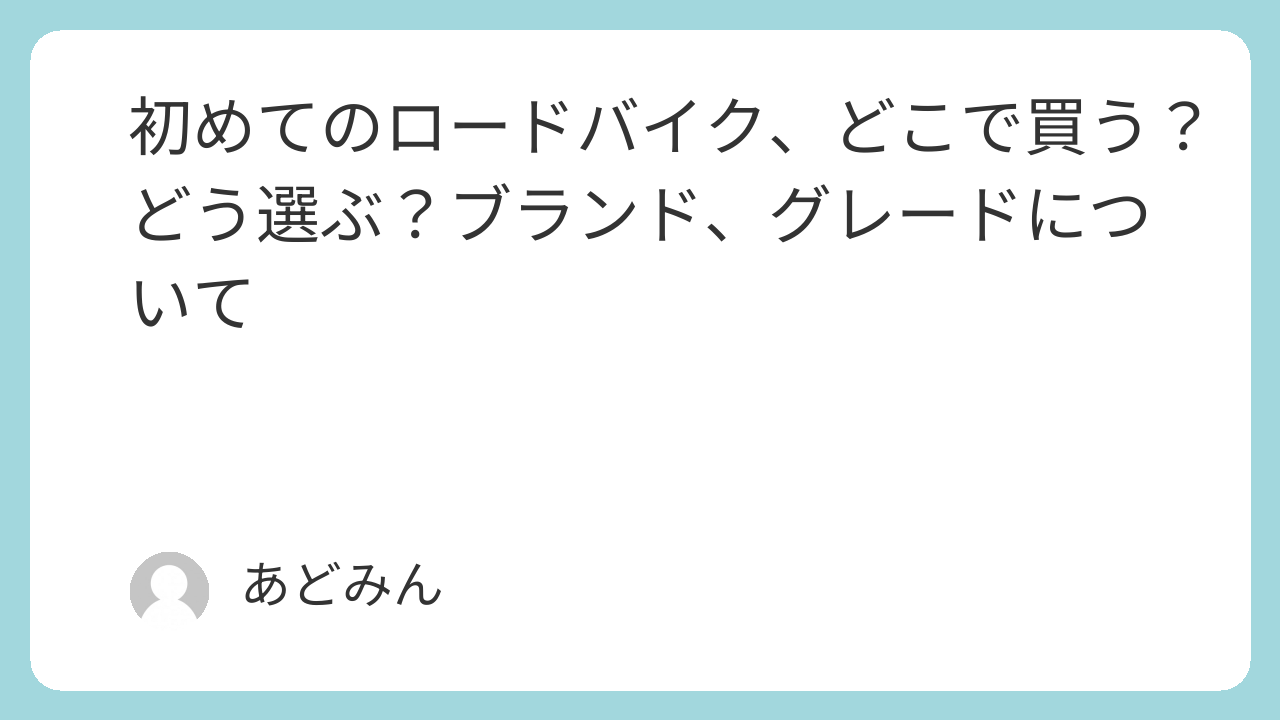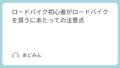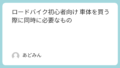ロードバイク初心者がロードバイクを買うにあたっての注意点
この記事の続きになります
どこで購入するのが良い?
新車で買うのであれば、近くにワイズロードがあればワイズロードで良いんじゃないかなと思います。
サイマやあさひでも新車は買えますが、
メンテナンスのことを考えると専門店のワイズロードのほうが良いです。
ネット上ではあれこれと言われていることもありますが、結局は対応した人次第なんですよね。
入れ替わりも激しいので今回接客してくれた店員が3年後も同じ店舗にいるとは限りませんしね。
あまり気にせずで大丈夫かと思います。
(ちなみに僕もどれにしようか探している時にワイズロードの店員に失礼な接客をされました。
が、必要品の購入もありますし、その後も普通に通っています)
もし家の近所に個人経営などの整備も出来るロードバイク専門店があるのであれば、
そういった所でも良いかと思います。
新車を買うのであれば、割引がどうとかよりも、後のメンテナンスで通える店で買うことの方が大事です。
僕は中古ショップのビチアモーレで買いました。
ネットで車体を見て、実店舗にて本物を見せて貰うことができるショップです。
ビチアモーレは整備済みで渡してくれるので、そのまま乗り出しても安心です。
その後のメンテナンスやパーツ交換なども対応してくれます。
サイクルパラダイスなど完全な通販サイトでは車体の事前確認をすることができませんし、
整備状態も分からないため、完全な初心者には全くお勧めできません。
自分で整備やオーバーホール(バラしてのグリスアップやホイールの調整、ワイヤー類の交換など)できる人が、
お、これは割安だぞ、という車体を買う場所だと思っています。
ただ、もしそういった通販サイトで買っても比較的リスクが少ないと言えるのは、
ここ3年以内に販売されたモデルで、定価で30~50万円以上するようなミドルグレード以上の車体です。
10年15年経った中古車にリスク(交換しないといけないパーツや交換目前のパーツがある)があるのは当然ですが、
3年落ち程度であれば、写真の見た目通りのコンディションで来る可能性が高いです。
とはいえ、そのような比較的新しい中古車体でも、
ビチアモーレやバイチャリなど、店舗で車体を確認して、またがってサイズ確認をして貰えるショップで買う方が、初心者の一台目としては安心できるかなと思います。
もし、近くに店舗があるのであれば、候補に入れるといいと思います。
ネットオークションやメルカリでの個人からの購入は、やはり知識が必要ですので、手を出さないほうが良いです。
とにかくフレームの見た目が気に入るかが大事
ここまでで、予算を大体決めて、なんとなく中古か新車かどちらが自分に向いているかな、というところを決めて来ました。
ここまで読んだということは、ロードバイクって結構大変なんだな、ということも理解して、
でも、やっぱり欲しいと考えていますね。
やっと、ロードバイクそのものの話になります。
この後考えるのは、メーカー(ブランド)、車体やフレームの見た目、グレード、この3つになります。
まずは車体の見た目、ロードバイクを購入するにあたって、本当にこれがとても大事です。
スペックがどうとか、素材がどうとか、パーツがどうとか、色々と考える要素はあるのですが、パーツ類は交換できますし、初心者~初級者のうちはパーツの違いよりも、ロードバイクに慣れる、乗りこなすことの方が大事です。
なので、毎日でも見たくなる、乗りたくなるような、大好きな色や見た目のフレームを選ぶのが大事だと思います。
僕の場合は、最初の候補はビアンキ(Biandhi)でした。
ティファニーが元々好きということもあり、
ティファニーブルーに似たこの色にグッと惹かれました。
しかし、後に購入することになるDEROSAを見つけ、実際に車体を見に行った時に
とてもかっこいい!と思い、弱虫ペダルの御堂筋くんが乗っているメーカーということもあり笑、
DEROSAに決めることにしました。
あとは、ビアンキは僕に合うサイズ感の中古が出ていなかった、というのも大きな理由の一つです。
まずはネットで良いので、色々なメーカーの車体を見て、気に入る見た目のメーカーを絞り込んでいきましょう
メーカーはどう決める?
僕は、上記のような見た目で絞り込みをしていくことで、
Bianchi、DEROSA、Pinalelloの3社に絞り込んでいきました。
僕はどちらかというとミーハーで所有欲もあるタイプなので、
名前の通っているブランドにしたいと考えていました。
なので、最初の選定でイタリア(ヨーロッパ)の老舗有名ブランドにする。
というような決め方をしました。
上記3社以外にも、ColnagoやSCOT、FELTなどのヨーロッパブランドもあれば、
TREKや、SPECIALIZEDなど北米の有名ブランドもあります。
また台湾のGIANTやMERIDAも有名ですし、販売数という意味ではGIANTは世界一ですね。
しかし、僕の中では老舗力やブランド力として抜きんでていると感じた、
Biandhi、DEROSA、Pinalelloの3社に絞った形です。
ブランド毎に、やはり見た目の特徴というものが出てくるかなと思いますので、
やはりフレームの見た目で決めてしまうのが良いかなと思います。
ピンと来るメーカーを見つけるためには、ネット上に転がっている色々な販売サイトを見るのが良いです。
ワイズロード(新車中心)、サイクルパラダイス(中古)、ビチアモーレ(中古)、バイチャリ(中古)などで、
過去に売れてしまったものも含めて、色々と見て、気に入る見た目のブランドを見つけましょう。
僕は今回はDEROSAにしましたが、今後新しいロードバイクを買うとしても、
Biandhi、DEROSA、Pinalelloの3社のどれかにするだろうと思っています。
フレームのサイズ感はとても大事、しかし・・
続いて、初心者の悩みどころがフレームのサイズだと思います。
47とか50とか書いてあって、よく分からないやつです。
まず前提としてフレームサイズというのはめちゃ大事です。
乗り心地や加速のしやすさ、疲れやすさなど、あらゆる要素にサイズ感が関わってきます。
多くの販売店では推奨の身長が書いてありますので、概ねはこれを参考にすればよいです。
新品で買うのであればメーカーが用意しているサイズから選べる場合が殆どですし、
新品ならワイズロードなどのショップに行けば、フィッティングを受けた上で買うことができます。
ただ、中古で探している場合に、気に入ったブランドの気に入ったフレームでドンピシャのフレームサイズのものがあるかどうかは、その時の運になります。
ワンサイズ違いくらいであれば、セッティングやパーツ交換で何とでもなる場合が多いですので、
フレームサイズだけにこだわって見逃してしまうのは勿体無いです。
これしかない!というくらい気に入った見た目の車体が見つかったならば、
ワンサイズのズレくらいは許容しても大丈夫です。
例えば、身長が175cmで、サイズの適応身長目安が167~173cm、
くらいであれば、乗っていてそこまで問題が出ることはありません。
というのも、手足の長さ、胴の長さ、体の柔らかさなど、人それぞれの身体的特徴がありますよね。
本来、フレームサイズや各種パーツのセッティングを考えるのならば、これら全てを考慮して考える必要があります。
初心者の段階で、これらをジャストに判定して、このフレームサイズにこのステム長、このクランク長がベストだ!なんて判断できませんよね?
(まず用語も分からないですよね)
「いやいや、新車で買うから、きちんとフィッティングして貰うよ」
と、思うかもしれません。
しかし、ロードバイクに乗ったことが無い人をフィッティングするのって、とても難しいことだと思います。
僕はロードバイクを購入して2ヶ月で500kmくらい乗りまして、
2~300kmくらい乗ったあたりで、サドルの高さやハンドルの高さによる足の回転のしやすさなどが分かるようになってきました。
サイズ調整が出来る部分については自分で調整をしていて、良いポジションはどこだろうかというのを探している段階です。
乗り始めの頃は購入したままのポジションで乗っていましたが、それが良いポジションなのか悪いポジションなのかなんて、さっぱり分かりませんでした。
なので、あくまでも適応身長は目安であり、乗ってから色々と調整をしていく乗り物だということです。
そしてその経験を2台目、3台目に活かしていく、というのがロードバイクの楽しみだとも言えます。
最初から自分にジャストなものを他人に提案して貰って買おうという人任せ根性ではなく、
愛着のあるブランドや見た目の車体にして、自分で良いポジションを探して行こう、という人じゃないと、そもそもロードバイクは難しいんじゃないかなとも思います。
使い道でグレードを決める
何となくメーカーも絞れてきましたかね。
しかし、ここでまた一つの疑問が出てきます。
「同じメーカーで同じような見た目なのに値段がなんでこんなに違うんだ・・?」
そう、グレードの問題です。
例えば、BianchiでもOLTRE、SPECIALISSIMA RC、PRO、COMP、SPRINT、VIA NIRONEなど、新車で買えるモデルでもいくつかのグレードがあります。
これを、どうやって選ぶのか?
要素は大きく分けて3つあります。
フレームの素材、コンポ(変速機やブレーキなど)、ブレーキの種類
です。
これらを考える前に、まず、あなたのロードバイクの使い道を考えてみて欲しいです。
使い道も、大きく分けて3つ、というか3段階あります。
1.通勤および週末のライドなどゆる~く乗るだけ
2.トレーニング用途としても使いたい
3.ゆくゆくはレースに出たい
どうでしょうか?
僕の最大の誤算は、1.のつもりで始めたのですが、
ちょっと乗ってみたら楽しくなっちゃって、近いうちにレースにも出たいなと思うようになったことです。
要するに、気質がアスリートなのかどうか、が重要になってきます。
過去に運動部に所属していたり勝負の世界を味わったことがある人などは要注意です。
きっと、ハードなトレーニングをしたくなり、レースにも・・。という気持ちが芽生えてきます。
そうではなく、もっとライトな運動不足解消や通勤を電車や車から自転車に変えようですとか、
サイクリングに行こうと誘われて週末にロングライドに行きたい、
というような使い道を想定しているか、ですね。
もし、あなたが
1.通勤および週末のライドなどゆる~く乗るだけ
であり、予算が限られているのであれば、
恐らくメンテナンスも自分でガッツリというタイプではないと思いますので、
新車
フレーム:アルミフレーム(フロントフォークだけカーボンならなお可)
コンポ:SHIMANOのTIAGRA(ティアグラ)以下でOK
ブレーキ:ディスクが選べればディスクが良いが、リムブレーキでもOK
※SHIMANOのコンポはグレードの高い順に、DURA-ACE(デュラエース)、ULTEGRA(アルテグラ)、105(イチマルゴ)、TIAGRA(ティアグラ)、SORA(ソラ)、CLARIS(クラリス)となっています
この辺りのグレード感、言わゆるエントリーロードが候補になると思います。
値段帯としては新車で15万円前後になります。
トレーニングで使う分には使えますが、
もし友達と軽く競争のように走るのであれば、物足りなくなる可能性があるのも、このグレードです。
また、パーツ交換をして速くしたいと思っても、車体の持つポテンシャルが低いため、カスタマイズの有用性も低くなってしまいます。
買った状態で、あとは自分に合わせた調整くらいで乗り続けるというのが基本になります。
トレーニング志向、レース志向があるなら絶対ミドルグレード以上
もし、トレーニングでもハードに乗りたい、友達と競争チックな乗り方もしたい、またその先にレースなんて夢もあるかも・・。
と、思うのであれば、ミドルクラス以上のグレードが候補になります。
新車でも中古車でも良いですが、
新車で30万円以上クラス、中古でも15~20万円前後が選びどころになります
予算が許すなら、それ以上のグレードでももちろんOK
フレーム:カーボンフレーム
コンポ:SHIMANOの105以上、無線である必要はない
ブレーキ:ディスクを選んでおくのが無難
まずブレーキをディスクにしたほうが無難なのはなぜかというと、
ミドルクラス以上のグレードの車体を買って、トレーニングやレースも視野にとなると、
ホイール交換が必須になります。
いわゆる完成車と呼ばれる、組み上げた状態で販売されている車体についているホイールは
重たいアルミホイールであることが殆どです。
別にトレーニングで乗る分には何でもいいのですが、見た目を追求したり所有欲も出てきますし、
何よりも、良いホイールに交換すると本当に乗り味が変わります。
自分の目指す方向性に合わせたホイールに変えたくなる時が必ずきます。
(ヒルクライム系なら軽いホイール、クリテリウム系ならディープリムホイールなど)
いずれにしても、カーボンホイールが視野に入ってきます。
何が問題かというと、カーボンのリムブレーキのホイールだと使えないチューブが出てきます。
(カーボンはアルミに比べて熱を蓄えやすく、ブレーキにより発熱するため、熱に弱い素材のチューブは破裂などの恐れがあり、使えない)
チューブは素材の種類があり、主に、ブチル、TPU、ラテックスの3種類があります。
このうち、ラテックスは絶対に使えません。
TPUはメーカーによっては使えるものもありますが、使い方に制限(長い下り坂などブレーク長く使う場面では推奨されない)が出てきます。
ですので、安全面を取るならばブチル一択となるわけですが、
ブチルは他の素材に比べると重いわけです。
ミドルグレード以上の車体を選び、ハードなトレーニングやレースも視野に、と考えた時に、
TPUやラテックスチューブを使えないのはマイナスになります。
そのため、ディスクブレーキを選べるならば選んでおいたほうが無難、ということです。
僕は2015年製のDEROSAを買いましたがリムブレーキでした。
購入時はこのような知識が無く、仮にあったとしてもこのDEROSAを選んでいた可能性は高いですが、
知って選ぶのと、実は後になって選択肢が少なかったというのを知るのでは、
やはり落胆の度合いが違いますからね。
本当はお勧めされているラテックスチューブでGP5000を試してみたかった・・。
その他の留意点
その他の面では、ハンドルステム一体型やケーブル類のフル内装モデルのハンドルは積極的に選ぶ理由はないかなと思います。
ハンドルステム一体型は調整の余地がないため、自分のポジションが決まってから選ぶものだと思います。
フル内装モデルというのは、ケーブル類がハンドルの中を通っているものです。
更にステム一体型のフル内装ですと、
STIレバー(ブレーキやギアチェンジをするレバー)の位置をちょっと変えたいと思っても、
ケーブルの取り回しが難しく、自分での調整はおろか、お店でもワイヤーを引き直さないと
調整できない、ということもあります。
最初の一台としては、エアロの内装モデルのハンドルではなく、
外装式のハンドルのほうがメンテや調整もしやすいです。
更に言うと、ハンドルはいずれ変えたくなることが多いです。
形やサイズ、素材などが色々とありますので、
パーツ交換もしやすいように、ハンドル回りは外装式を選んでおくほうがやりやすいです。
まとめると
新車ならワイズロードか整備も出来るロードバイク専門店でフィッティングをした上で購入
ブランドは知識が無いなら有名どころを選んだ方が良い
なによりも、見た目が好きという感覚が大事!
フレームサイズは大事だけれども、
見た目が気に入ったのならばワンサイズのズレくらいは許容して良い!
グレードは使い道で決める
ハードに使わないならアルミフレームのエントリーグレード(新車価格15万円)で良い
乗るぞ!と思っているならカーボンフレームで105以上のミドルグレード(新車価格30万以上)以上を選んだ方が良い
メンテナンスしやすいモデルを選んだほうがいい
最初は色々といじって覚えられるように、触りやすい作りの車体を選んだ方が良い